| バックナンバー | |
| 2002年4月 | とらえ離さぬ時間 |
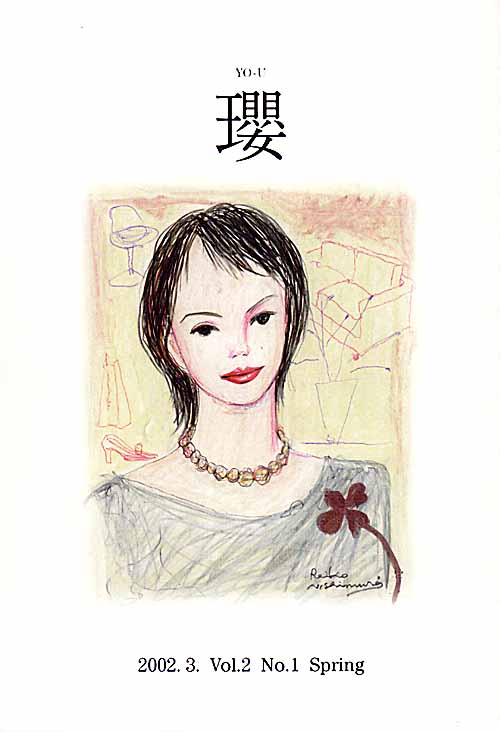
雑記 2002年6月
|
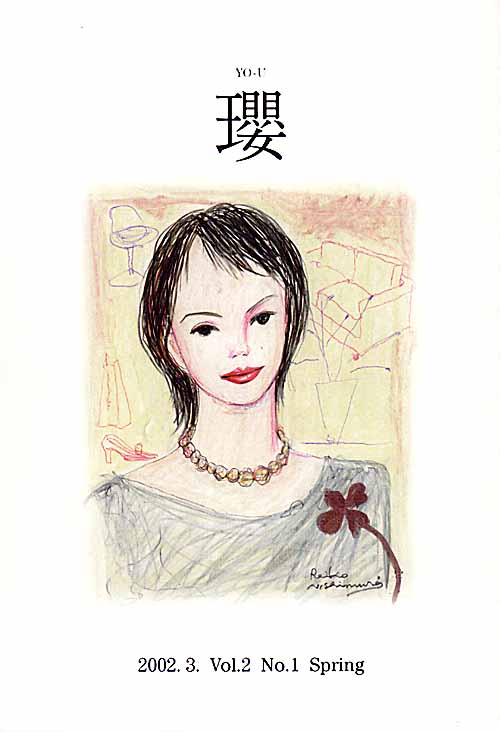 |
| 花と知るべし ー飯倉八重子句集「草眸」よりー 加藤いろは
「能」と「俳句」は、よく似ている。 ただのかくれんぼ遊びかもしれないのに「少年墓に隠れけり」というフレーズには、得たいの知れぬ不安がつきまとう。子が母を探し、母が子を探すという、古典的悲劇の最たる能「隅田川」が、或は、八重子の胸中を過ぎったのか。劇中では、梅若丸の霊は、母の手をすり抜けて塚へ入ってしまう。亡くした子供は、永遠に子供のままだ。そして、喪失感を抱いたまま、母ひとり老いてゆくのか。 ☆ ☆ ☆ ギリシア神話のみならず、人と人でないものとの交流は日本にも、いろいろなパターンで伝えられている。そのうち羽衣伝説のいくつかは、天人が鶴や鷺、白鳥の姿を借りて出現する。八重子の眼がとらえた「夜飛ぶ鳥」とは、実は、此岸から彼岸を渡る、魂の象徴のようなものではなかったのだろうか。不思議な昂揚感にあふれた句である。 夢みるによし冬しだれ木の中は 八重子 能舞台という空間は、「中有」(ちゅうう)という宗教的概念を思わせる。「中有」。それは、この世とあの世の間の時空。次に生まれるまで魂の居る処。案外「冬しだれ木の中」にもあるのかもしれない。夢をみているのは、八重子なのか、八重子以前のものなのか。誰かが触れるまで眠っているのだろう。 ☆ ☆ ☆ 八重子の句の本質は、抒情であったのだが、言葉を厳しく選ぶことによって、八重子スタイルという個性を作り出したのだ。そういう意味でも、この句集『草眸』は、彼女の世界が、もっとも輝いていたといえるだろう。
|