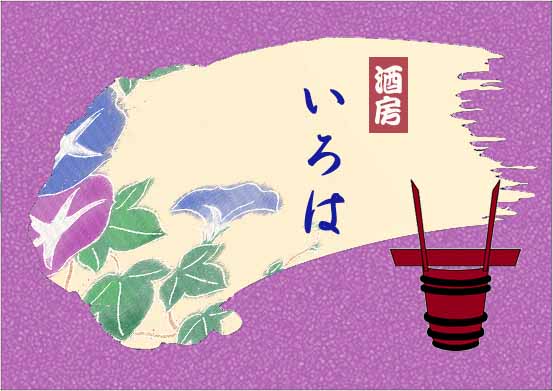
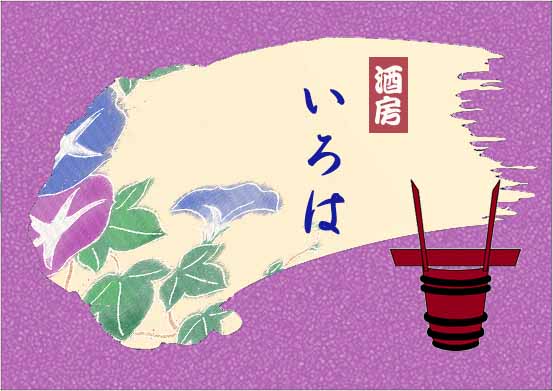
2000年7月25日更新
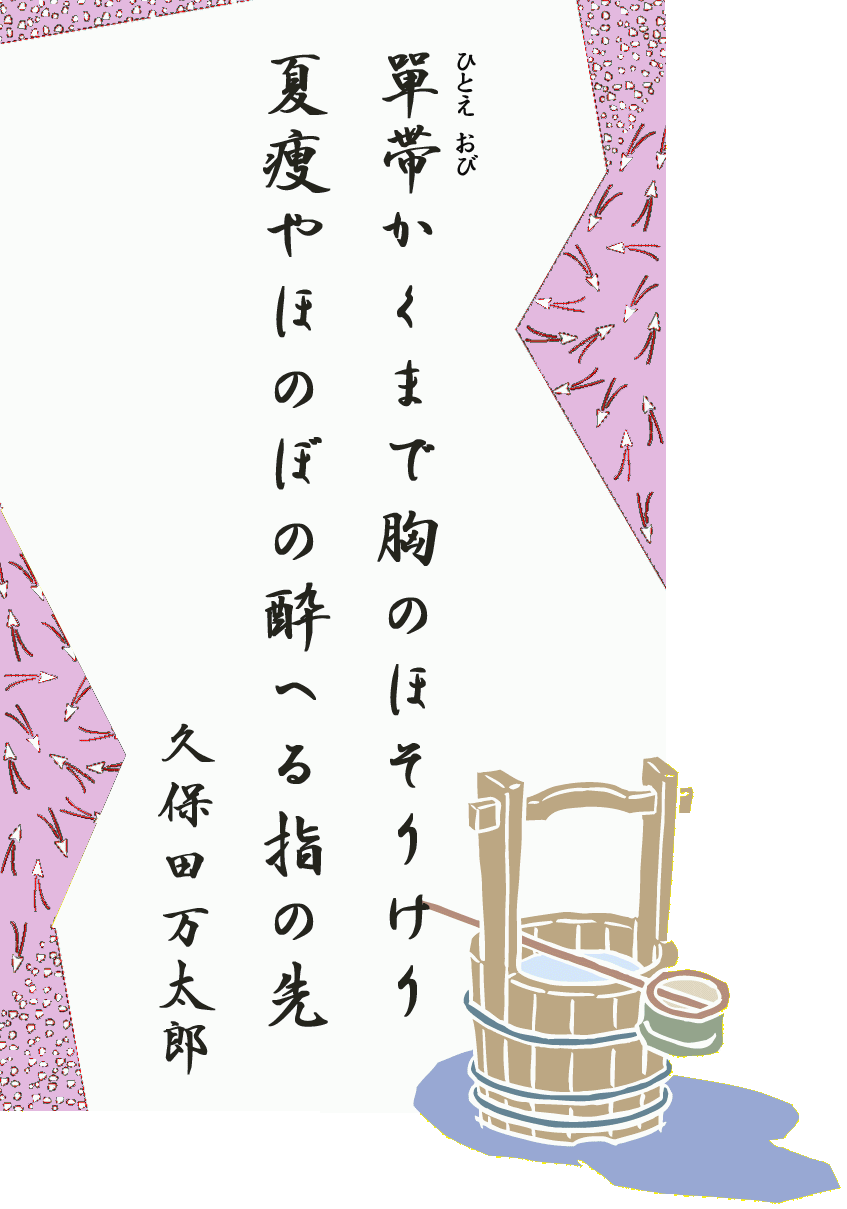 |
昭和二十一年作 |
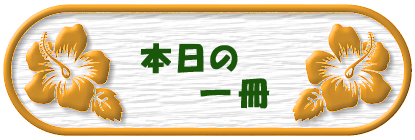
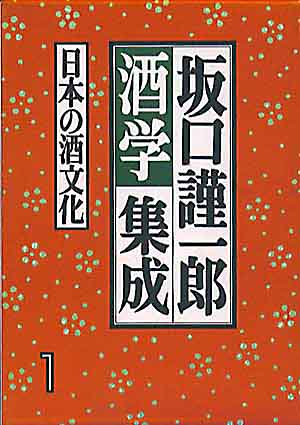 1998年 岩波書店 |
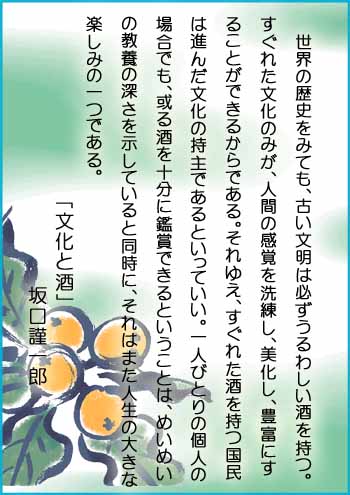 |


|
稲作儀礼と
池浦秀隆
|
稲作の伝来より二千数百年。日本はお米の国であります。社会経済史・食文化・精神文化等、米が果たしてきた役割を鑑みれば切りがありません。柳田民俗学の世界では、水田稲作農耕民の基本的な思考が、日本人のものの考え方や世界観の中心になってきたとしています。それは、経済大国に達した現代日本において、今もなお年中行事や暦の源となり、日常生活を規定し、基層文化として機能しているといえます。 さて、古の社会において、稲作の成否が人間の死活に関わってきたことはいうまでもありません。全国の津々浦々では豊穣を願う“植物と人間の交感”がおこなわれ、たくさんの伝統的な稲作儀礼が今に伝わっています。それは、春夏秋冬1年のサイクルに稲の生育という条件を加えて展開されます。 阿蘇神社の年中行事は稲作儀礼が中核をなしています。稲の生育過程に合わせた祭日が設定され、芸能的・娯楽的な要素を加えつつも、大自然の恵みに感謝する素朴な古の人々の祈りが“かたち”としてよく現れています。個々の祭礼は稲作儀礼の典型であると位置付けられ、昭和57年に国重要無形民俗文化財に指定されています。しかし、観光的な絡みから、近年は映像的に見応えがある「火振り神事」だけが注目されるようになったことは残念なことです。 7月28日に行われる御田植神幸式は通称「おんだ祭」とも呼ばれ、阿蘇神社の年中行事の中で最大規模のものです。神様がお乗りになられた4基の神輿を中心に、田男・田女・牛頭などの農耕に因んだ人形等、神様のお食事を運ぶ役を担った全身白装束の「宇奈利」と呼ばれる女性たち、約200人の行列が青田の中を練り歩きます。この時期の稲の育ち具合を神様にご覧頂くことによって、秋の豊作を祈願するものです。 お祭りの名称は御田植神幸式というものの、実際に田植えを行うものではありません。すでにこの時期の稲はかなりの背丈まで成長しています。では何をもって田植とするのでしょうか。行列には定められた道順があります。神社を出発して途中2カ所のお仮屋(休憩所)を経て再び神社に戻ってきます。さて、行程の中で2ヶ所のお仮屋と帰着後の神社において、神輿にむかって稲が投げかけられます。この行為が“田植え”と称されています。稲は御田祭用に特別に育てられた神事用のものが使用されます。そして、たくさんの稲が神輿にのれば豊作になるとされています。 行列は、約半日をかけて駕輿丁(かよちょう、神輿を担ぐ人たち)が御田歌を謡いながら遅々と進んでいきます。古式ゆかしい、のどかな時代絵巻が展開されます。 見学の方々には、豊作を願う古人の“こころ”を感じて欲しいです。 |
| プロフィール
池浦秀隆 |
出身は福岡県、熊本育ち 学生時代は国史学を専攻していました。現在、阿蘇神社を歴史と民俗の2つの柱で考えるようにしています。常に文化的な見地から、神社の独自性の中に普遍性を見出し、たくさんの方にご理解いただけるよう心掛けています。 |
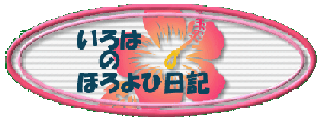
| 文月 某日 山上祭
「山上祭」は阿蘇の噴火を鎮める神事です。本来ならば、先月行なわれるはずだったのですが、火山ガスによる立入り規制が続いたため、今月になりました。
|
バックナンバー